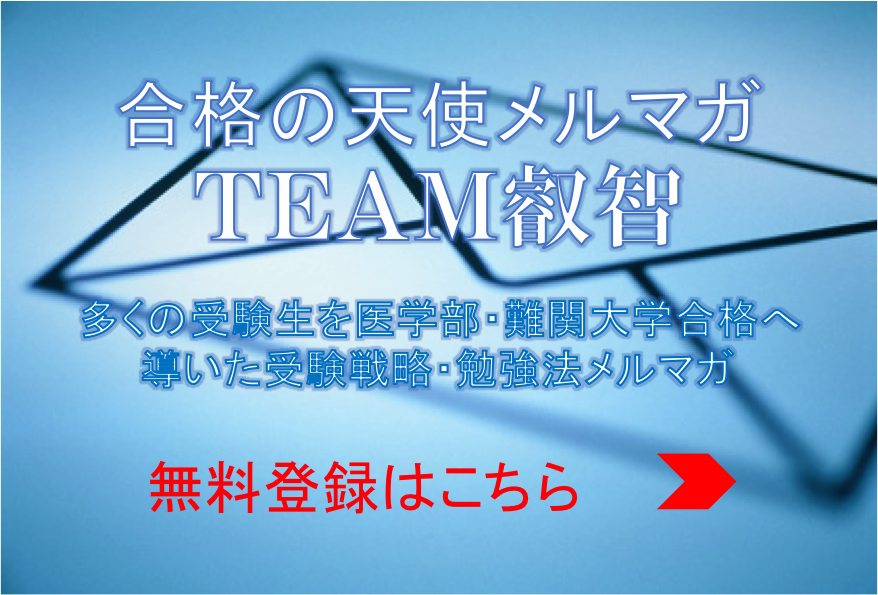公式サイトトップ>> 無料のネット塾>> センター試験勉強法と対策法>> センター化学の勉強法|9割超への対策
センター化学の勉強法
9割超への対策
東大理三合格講師30名超によるセンター化学の勉強法と9割超への対策
センター化学の門外不出の講義を開放します!
センター化学の勉強法の解説に入る前に、お知らせをさせていただきます。
多くの受験生をセンター試験9割超へ導いてきた門外不出の講義であるセンター化学講義を当塾の受講生以外にも開放します。当塾講義は講義の機密性保持の観点から3か月以上継続受講の個別指導受講生以外のお申し込みはお断りさせていただいてきていました。本来個別指導受講生以外は視聴が出来ない講義です。
しかし、センター試験が最後となる本年度一般受験生への開放を行います。自身が実際にセンター化学で満点を獲得している東大医学部(理三合格)講師を30名以上擁する叡学舎(株)合格の天使の検証と結果に裏付けられたセンター化学対策講義です。徹底的に化学のセンター試験対策をしたい、センター化学で高得点を獲得したという方は是非この機会を逃さないでください。一定数のお申込みで募集を終了します。センター化学を効率的に完全攻略するための講義です。
センター化学講義の詳細及び破格の受講料・お申し込みは以下のページへお願いします。
センター化学の勉強法と対策
センター化学の勉強法と対策では、センター化学で9割超の得点を獲得するための勉強法、 センター化学で高得点を獲得するための勉強法と対策についてお伝えしていきます。 文系受験生、理系受験生を問わずセンター化学で9割超、満点を目指しましょう。
センター化学の勉強法と対策のコンテンツでは、実際にセンター化学で満点(100点),9割5分超を獲得している
センター試験 872/900点獲得 東大理三合格講師槇(東大医学部医学科)
センター試験 881/900点獲得 東大理二「首席」合格講師大久保(東大医学部医学科)
センター試験 867/900点獲得 東大理三「次席」合格講師(東大医学部医学科)小団扇
センター試験 877/900点獲得 東大理三合格講師(東大医学部医学科)安藤
センター試験 851/900点獲得 東大理三合格講師(東大医学部医学科)花村
センター試験 828/900点獲得 東大理三合格講師(東大医学部医学科)佐伯
センター試験 9割超獲得 東大理二合格講師 山本
による動画、音声動画も交えセンター化学の勉強法、センター化学で9割超の得点を獲得するための勉強法、センター化学で高得点を獲得するための勉強法と対策についてお伝えしていきます。
このコンテンツは1000以上のコンテンツを誇る叡学舎・叡学会(株)合格の天使のブログ及びメルマガからセンター試験化学に関する記事を抜粋したものです。簡潔にセンター化学対策のポイントを明示します。ポイントの意味をよく理解してセンター化学で高得点、満点を獲得してください。
【コンテンツ 目次】
(3)センター化学の勉強、対策の開始時期~センター化学対策と2次試験化学対策のバランス~
(5)【動画】「センター化学完全攻略レクチャー」『中和滴定』
3.センター化学 満点・9割5分超獲得者による具体的な勉強法と対策
(1)化学の基礎力不足の状態でのセンター過去問演習は意味がない
(2)二次対策として基礎を固めればセンター化学も自ずと満点近くまでいく
(1)センター試験対策に早い時期に特化するのではなく受験化学の基礎をしっかり身に着ける
(1)センター化学と2次試験・私大対策を効率的に行いたい受験生へ
(3)高得点が取れないのはセンター化学対策が十分でないからではない
(4)センター化学の勉強や対策で心がおれそうなときに読むコンテンツ
センター化学の問題の特徴と大問ごとの分析
センター化学の具体的な勉強法や対策の前に、まずはセンター化学でどのような分野がどのように問われているのか、を知っておくことが9割、満点を獲得するために大切になります。
以下では、当塾、東大理三合格講師陣による、センター化学の大問ごとの分析を交え解説していきます。
出題分野
センター試験の化学の出題分野としては、大問1から大問7まで順番に、物質の構造・状態、物質の変化と平衡、無機物質、有機化合物、高分子化合物、合成高分子化合物、天然高分子化合物と出題されています。
平成29年度と平成28年度は第6問と第7問のどちらか一題を選択、平成27年度は第5問と第6問のどちらか一題を選択という出題でした。
物質の構造・状態
毎年小問6題(各4点)が出題されています。
どの問題も教科書の例題レベルの問題で、細かい知識が問われたり、複雑な計算が出題されることはありません。 基本的な用語の意味を正しく理解できているか、教科書レベルの計算問題をしっかりと解けるかが重要です。
分野としては物質の状態変化や結晶格子の問題、気体の計算問題などがよく問われる傾向にあります。
物質の変化と平衡
毎年小問6題(各4点)が出題されています。
計算問題がメインですが、問題は標準的かつ典型的なので教科書の例題、 過去問をしっかりと練習すれば対応できます。
熱化学方程式、気体の平衡、酸化還元反応が問われることが多いですが、 パターンは毎年あまり変わっていません。
熱化学方程式で言えば、熱化学反応式や生成熱などの条件が与えられてそれをもとに計算する問題、 酸化還元反応で言えば、半反応式が与えられてそれをもとにmol計算をする問題などです。
センター試験では半反応式が与えられるか、 与えられない場合は化学反応に関わる物質が全て与えられるため係数比較法から化学反応式を導けます。 そのためセンター試験の化学を解くだけなら半反応式を覚えなくても解けますが、 2次試験では半反応式を自分で作る必要がある問題が出題される大学が多いので半反応式はしっかりと覚えておきましょう。
無機物質
無機物質に関する知識を問う問題と、知識をもとに計算する問題に分かれます。 知識問題はもちろん教科書に掲載されている範囲からしか出題されませんが、 年によってはかなり細かいところまで聞かれる問題が出題されることもあります。
計算問題ではアンモニアソーダ法やハーバー・ボッシュ法など典型的な反応が問われたり、 酸化還元反応の問題が出題されたりしています。 また27年度の第3問問6など一見見慣れないような問題が出題されることがありますが、 問われている知識は基本的なものにすぎませんから、柔軟にそれを応用させることで対応できます。
有機化合物
有機化合物に関する知識を問う問題と、計算問題に分かれます。 知識問題では各々の有機化合物の性質はもちろん、 構造式をしっかりと書けるかが解答のポイントになっている問題が多いです。
計算問題では官能基に特有の反応(ヒドロキシ基とナトリウムで水素が発生するなど) について計算する問題が多いため、どのような反応が起きているかについての知識が前提となっている。
高分子化合物
過去問では知識問題のみが問われており、計算問題の出題はなされていません。 日常生活の中で高分子化合物がどのように使われているかや各高分子化合物についての性質、 生成法について問われています。細かいところまで出題される事もあります。
知識問題は教科書に載ってはいるものの、2次試験では問われないような内容が問われることが多いので 満点を目指すなら教科書のチャックは行ってください。
合成高分子化合物
知識問題と計算問題が出題されています。 計算問題の題材となるのは典型的な高分子化合物であり、 計算内容は若干難しいものもありますが、教科書や傍用問題集の演習で十分対応できる内容です。
天然高分子化合物
29年度はペプチド・糖から、28年度はペプチド・核酸から、27年度はペプチド・糖・核酸からの出題でした。 計算問題と知識問題が出題されています。 知識問題は若干細かいものも問われますが、計算問題は基本的な問題ばかりです。
センター化学の出題の特徴
【センター化学満点/センター試験872/900点獲得東大理三合格講師槇】
センター化学の全体的な特徴として、相当細かい知識まで要求されるということがあげられます。特に知識 問題ではすべての選択肢の正誤が判断できないと一つに絞り込めませんから、幅広く正確な知識を持っていないと正解にたどり 着けません。
実際のセンター試験問題を見てみよう
試しに2012年度の化学のセンター試験の一番最初の問題を見てみると
単体でないものを選べ ・黄銅(しんちゅう)・亜鉛 ・黒鉛 ・斜方硫黄 ・白金 ・赤リン
という問題です。
これは頻出問題で、答えは銅と亜鉛の合金である黄銅ですが、それだけ知っていても斜方硫黄、赤リンがそれぞれS,Pの同素体 であることを知らないと絞り込めませんね。
実際の出題から分析する9割超・満点への道
今のは単純な問題でしたが、第3問などでは無機化合物に関するさらに詳細な知識を持っていないと絞り込めないものが多くあ ります。
したがってセンター化学の過去問演習を繰り返しつつ適宜教科書や参考書に戻りセンター化学で出題される知識を盤石なものに していくということがセンター化学で9割超~満点を獲得するポイントになります。
二次試験問題との性質の違い
大学の二次試験では理論問題、計算問題が重点を占め、 センターほど知識が必要とされない場合が多くなるため、 二次対策だけでは乗り切れないのがセンター化学の特徴です。
センター化学の勉強法と対策の基本方針
センター化学の勉強法と対策の基本方針として、センター化学対策として最もおすすめな参考書や問題集は何?という話やセンター化学対策として何をやればいいのという勉強法の基本方針について解説していきます。
理系受験生のセンター化学の勉強法と対策の基本方針
【化学選択「理系」受験生】
2次・私大試験がある理系受験生は化学の教科書、傍用問題集(生物の教科書代用書・代用問題集)で基礎を徹底的に習得し(※この点については当塾が提唱する 「教科書学習の重要性」▶のコンテンツを参照)、受験標準問題集で受験標準知識としての解法やパターン、対処法を学び志望校の過去問演習でブラッシュアップしていく⇔センター過去問演習の往復(サイクル学習)でセンター試験の細かい知識問題の知識の穴埋め、2次試験対策の補充という方針をおすすめする。
この点について更なる詳細を学びたい方は 「受験の叡智」【受験戦略・勉強法の体系書】を ご覧ください。
文系受験生のセンター生物の勉強法と対策の基本方針
【化学基礎選択「文系」受験生】
センター試験しかない文系受験生はセンター試験 化学基礎の点数が面白いほどとれる本等のセンター試験向け参考書
で基礎知識の習得⇔センター過去問演習の往復で徹底的に穴を埋めていくことをお勧めする。(教科書も適宜利用。※この点については当塾が提唱する
「教科書学習の重要性」▶のコンテンツを参照)
高得点を目指すなら化学基礎の教科書、傍用問題集(生物基礎の教科書代用書・代用問題集)で基礎を徹底的に習得⇔センター過去問演習とのサイクル学習を繰り返すのがベター。 ただし他の教科との兼ね合いを十分に考慮すること。
この点については、センター化学基礎の勉強法|9割超への対策をご覧ください。
更なる詳細を学びたい方は「受験の叡智」【受験戦略・勉強法の体系書】を ご覧ください。
センター化学の勉強、対策の開始時期~センター化学対策と2次試験化学対策
【センター化学満点/センター試験872/900点獲得東大理三合格講師(東大医学部医学科)槇】
理系で二次とセンター両方で化学をとっている方は特にですが、化学におけるセンター対策は計画に余裕があれば他の科目より早めに始めたほうが良いでしょう。(後述しますがセンター化学の知識問題だけに特化した対策は12月からが最終リミットです)私の場合は9月からセンター化学(と倫政経)の過去問を解き始め、最終的には本番までに約20年分を2周しました。
このように重点を置いたのは、センター対策としての他に、二次試験に向けた知識の穴埋めのためでもあります。二次試験でも知識問題はありますし、理論的には問題が解けても知識がないために解けない、ということもあります。そのため、過去問を解きながら知識の抜けに気づいた部分は適宜参考書で確認しながら、暗記カードに書き出して覚えることで知識の補完をしていました。
センター数学では二次対策で養った力がセンター対策にも適用できるものですが、センター化学では逆にセンター対策を通して二次対策がより盤石になるという側面があります。基礎が完成してきたら、センターと二次それぞれの対策を両輪のように進めることで、相互に有益なものになります。
※二次・私大対策も含め化学の勉強法と対策を学びたい方は化学の勉強法と対策も併せてご覧ください。
化学のセンター対策として最もおすすめな問題集
他科目のところでも述べているように問題演習はマーク式の問題集とかそういった類のものではなく、「センター化学の過去問」を優先させてください。
過去問の重要性についてピンと来ない方は「過去問至上主義」「過去問至上主義を貫け」(著作権保護・無断使用禁止・要引用明記)について詳しく解説してある「受験の叡智」【受験戦略・勉強法の体系書】をご覧ください。
注意:化学の新課程部分や化学基礎を選択する文系受験生については問題数が十分ではありませんのでその部分だけは各予備校のセンター模試問題集等を利用していきましょう。
化学のセンター過去問集はなんでも構わない
センター化学の過去問集は何でも構いません。基本的に解説が詳しいとか、レイアウトが好きだとか、分量的にどうだとか、そういったことで個人の好みに応じて選んでください。
大事なことはセンター化学の過去問から得るべきものをしっかり得ることができるかどうかだけです。以下に代表的な予備校さんのセンター化学の過去問集を掲載しておきます。
■センター試験過去問研究 化学 (2018年版センター赤本シリーズ)
■大学入試センター試験過去問レビュー化学基礎・化学 2018 (河合塾シリーズ)
■大学入試センター試験過去問題集化学 2018 (大学入試完全対策シリーズ)
■大学入試センター試験過去問題集化学基礎 2018 (大学入試完全対策シリーズ)
センター化学の過去問の入手方法
センター化学の過去問集や参考書等を購入する場合に大きな書店が遠いとか、時間がないという受験生の方は以下を参考にし てみてください。ここに掲載するものは信用できるところのみです。
■Amazon(トップページ)
■セブンネット(学習参考書ページ)
■ hont(本ページ)
■楽天ブックス(学参ページ)
■e-hon(本ページ)
■紀伊国屋web store(トップページ)
■丸善&ジュンク堂 ネットストア(学参ページ)
センター化学の問題特性を考慮した勉強法のポイントとコツ
センター化学の問題特性を考慮した勉強法のポイントとコツとして、実際にセンター化学で100点・満点を獲得している当塾の東大理三合格講師槇(東大医学部医学科)、東大理二「首席」合格講師大久保(東大医学部医学科)によるセンター化学の特徴を分析した勉強法のポイントとコツを解説していきます。
センター化学で満点、9割超の得点を獲得するためには、まず、センター化学の出題特性を踏まえた勉強法と対策をしっかり押さえましょう。
センター化学の知識問題の勉強法と対策のポイント
【センター化学満点/センター試験881/900点獲得東大理二トップ合格講師(東大医学部医学科)大久保】
細かい知識が要求されるので注意が必要です。理論分野は2次試験の対策の中で同じ範囲をカバーしきれるので問題ないですが、有機・無機分野では2次試験にはあまり出題されないところが出たりしますのでセンター前に確認しておいてください。
たとえば有機物質であれば、製法は穴になりやすいですし、無機分野ならば製品への応用方法などが穴になるかと思います 。とにかく正確に正確に、を意識することが大事です。(センター化学に限らずセンター試験全般に通じる話ですが。)
センター化学の計算問題の勉強法と対策のポイント
【センター化学満点/センター試験881/900点獲得東大理二「首席」合格講師(東大医学部医学科)大久保】
化学の問題でも、計算過程は丁寧に順を追って問題用紙に書いていくことをおすすめします。焦っていると問題用紙にバラバラに殴り書きのように計算する方もいると思うのですが、試験本番に思わぬミスを引き起こしたりするので、正確に丁寧な計算を心がけましょう。
※センター数学の勉強法と対策のところでも述べていますが、計算ミスというのは大きな失点を招くものです。しかしこれをセンター試験本番で犯せばその問題について正確な知識がない人や全くできない人と結果は全く同じなのです。
「本当はできたのに」とか「ミスしたから実力が出せなかった」というのはセンター試験本番では全く通用しません。試験は結果がすべてです。ミスを甘く見ないでミスを少しでも防ぐ対策は地道に行っていってください。
センター化学の選択肢問題の勉強法と対策のポイント
【センター化学満点/センター試験881/900点獲得東大理二「首席」合格講師(東大医学部医学科)大久保】
選択肢問題でも、一つ一つの選択肢を丁寧に検査して排除していく消去法が使える場面では積極的に使いましょう。 誤ったものを選ぶのか、適切なものを選ぶのか、というのも化学の問題でひっかかりやすいところの一つです。センター化学の過去問演習を通じてしっかりと対策をしていきましょう。
センター化学の正誤判定問題の勉強法と対策のポイント
【センター化学満点/センター試験881/900点獲得東大理二「首席」合格講師(東大医学部医学科)大久保】
正誤判定問題は記憶した知識だけに頼るのだけでなく、知識がなかったとしても、持っている知識に基づいて自分で想像できるように普段から訓練しておくと良いでしょう。
つまり、普段から「なぜそうなるのか」をある程度のレベルの理由付けを自分でしながら記憶するという作業をすることが重要になってきます。(これはセンター化学のみならず化学の理解自体をかなり深めます。)
【動画】「センター化学完全攻略レクチャー」『中和滴定』
「センター化学完全攻略レクチャー」の講義動画の一部の無料提供です。何度も言いますが、センター試験の問題というのはセンター化学に限らず出題の傾向とパターンがある程度決まっています。要するに覚えるべき知識の範囲も明らかで、それをどうセンター試験でアウトプットできるか、そしてそのためにどう日々の勉強で知識を使えるものとして頭の中に整理していけるかが勝負になります。過去問演習を通じてしっかりと学んでいってください。
日々の過去問演習でセンター化学の問題にどう取り組みどのように思考して知識を整理して行くかの参考にしてください。センター化学で確実に高得点を獲得し第一志望校合格を引き寄せてください。難関大学や医学部医学科を目指される方はセンターでの高得点が必要になって来る場合も多いですので詰めを誤らずに第一志望校合格へ向かってくださいね。
【センター化学満点/(100点)センター試験872/900点獲得東大理三合格講師槇】
センター化学満点・9割5分超獲得者による具体的な勉強法と対策
以上述べてきたことを前提に、センター化学で100点満点を獲得している当塾の講師である、
センター試験 867/900点獲得 東大理三「次席」合格講師(東大医学部医学科)小団扇
センター試験 877/900点獲得 東大理三合格講師(東大医学部医学科)安藤
センター試験 851/900点獲得 東大理三合格講師(東大医学部医学科)花村
センター試験 828/900点獲得 東大理三合格講師(東大医学部医学科)佐伯
センター試験 9割超獲得 東大理二合格講師 山本が
具体的にセンター化学の勉強法と対策として何に着目し何を行ってきたかを特別公開します。
化学の基礎力不足の状態でのセンター過去問演習は意味がない
【センター試験877/900点獲得 東大理三合格講師(東大医学部医学科)安藤】
センター化学で得点できないとすれば単純に基礎的な実力不足ではないかと思います。センター演習をして「慣れ」ていっても点数が伸びていかないということです。
センター化学は教科書の問題や問題集にあるようなものと問題タイプが似ています。普段解いているものと似たものが出てきますから、点数が取れないならそれは慣れていないからではなく理解度が低かったり覚えるべきものを覚えていないからと考えられるのです。
ですのでただ過去問演習をしても伸びにくいと思われます。
ただ過去問演習が重要でないわけではありません。過去問は穴や苦手分野を見つけるために使って、その分野については参考書で考え方を再確認したり問題集で類題の解き方を確認したりして対応してください。ここではなぜそうなるのか、そう解くのかという点に注意してください。
二次対策として基礎を固めればセンター化学も自ずと満点近くまでいく
【センター試験867/900点獲得 東大理三「次席」合格講師(東大医学部医学科)小団扇】
センター化学は二次試験の化学と大して変わりません。全範囲から満遍なく基礎問題が出題されます。なので、二次対策として基礎を固めれば、センター化学も自ずと満点近くになります。
ただし、二次対策は計算問題が多いので、細かい知識が多少かけていても困ることは少ないのに対し、センター化学は重箱の隅をつつくような問題が出されるので、教科書を隅から隅まで読んで、知識を細かいところまで身につけないといけません。
12月になったら教科書を細かいところまで読むようにすれば対策としては十分だと思います。
センター化学の計算問題対策と知識問題対策
【センター試験867/900点獲得 東大理三合格講師(東大医学部医学科)佐伯】
センター化学の計算問題については、基礎を身につけて冷静になってやってみれば難しいと言える問題はあまりないはずです。
間違えたとしたら、作題者側が予想したありがちな間違え方にまんまとハマってしまっている可能性が高いです。どうして間違ったのかしっかり分析して同じ間違いは繰り返さないようにしましょう。知識問題については解いてみると、意外と知らなかったり抜けていることが聞かれて困ることもあるかもしれません。そんな時は、この機会に教科書を一冊読み込んで抜けている知識を埋め直せると二次試験対策にも役立つはずです。時間の無駄とか思わずに一回やってみることをおすすめします。
化学の知識も単なる暗記ではない!
【センター試験851/900点獲得 東大理三合格講師(東大医学部医学科)花村】
化学は暗記というイメージが強い人がいるとおもいますが、化学式や反応の組み合わせは全くの暗記では無く、多くの法則性があります。特に有機・無機・高分子では覚えるべき事項が多いですが、実は多くの反応や性質は、理論分野で学んだ事項の応用であることが多いです。
理論分野の中でも酸塩基・酸化還元・平衡定数は特に有機無機両方で頻出の概念です。もしも、理論や無機の勉強が単調な暗記だと感じているのならば、今までの分野と関連づけてそれぞれの反応を見直してみると、復習にもなりますし反応式の意味も理解出来て印象に残りやすくなると思います。
新課程分野は予想問題集も
【センター試験9割超獲得 東大理二合格講師 山本】
12月頃からセンター試験の対策を始めました。 新課程になって2年目だったため過去問は少なく、各予備校が出しているような予想問題集も一冊(5回分)やりました。それに加えて、教科書を精読しました。
理論分野でスムーズに立式出来るかなども大事だと思いますが、細かい知識の抜けもそれ以上に点数に響いてくるので、教科書や資料集を用いて知識を確認しておくことが特に重要だと感じました。
満点・9割超を獲得するために不可欠なこと
以上見てきた通り、センター化学で9割超~満点を確実に獲得するためには二次・私大対策の過程で行う受験化学の基礎の習得を最優先に行い、センター過去問演習を通じて、センター試験の化学の問題特性に応じた知識問題のインプットや計算問題のアウトプットが不可欠になります。
センター試験対策に早い時期に特化するのではなく受験化学の基礎をしっかり身に着ける
センター化学で高得点を獲得するためには、理系受験生は計算問題の基礎力をつけるためにセンター過去問を用いるのではなく、まずは二次・私大対策を行う過程で受験化学の基礎力をつけることが最優先です。
知識問題対策として教科書をしっかり頭に入れる
知識問題に必要となる知識も二次・私大対策でついていきますが、センター化学特有の細かい知識については、センター過去問⇔教科書のサイクル学習(著書「受験の叡智」【受験戦略・勉強法の体系書】のキーワード・キーフレーズ)で地道につぶしていく必要があります。
センター試験直前期の化学勉強法のポイント
センター試験まで残り1~2か月で多くの受験生は本格的にセンター化学対策に入っていきます。 ここからやるべきことをやればセンター化学の点数はシッカリ上がっていきます。 残り期間で着目すべきポイントを当塾東大理三合格講師陣が各教科動画収録してくれてあります。 是非参考にしてください。
残り1~2か月のセンター化学の勉強法のポイント
以下の動画内で解説していますが、残り期間で受験生各自の現状に応じてやるべきことのポイントは変わってきます。 センター化学の得点が5~6割の方はとりあえず8割を目指してください。ここでのポイントはまず8割をとるための勉強法を実践するということです。 8割を獲得する勉強法を実践したほうがはるかに効率的でありいきなり9割超~満点を目指す勉強法はとらない方がしっかり実力もついていきます。この点は要注意です。
現状で8割以上の得点を安定して取れる方は9割超~満点を取るにはどうしたらいいかを学んでください。 センター化学で9割超~満点を獲得するにはあるポイントに着目して詰めを行っていくことが必要になります。 この点については以下の動画内で解説していますのでご覧ください。
【動画】残り期間で8割、9割超~満点をとる方法
センター化学で8割を目指す人と9割超~満点を目指す人向けに、何に着目して勉強していけばよいかを解説した動画です。是非ご覧ください。
センター化学の勉強法と対策 まとめ
以上簡潔にセンター化学の勉強法、対策のポイントについてお伝えしてきました。これだけで圧倒的高得点・受験結果に実証されたセンター化学の受験対策と勉強法をあなたは手に入れています。
多くの受験生が踊らされる実際の自身のセンター得点を明示していない(できない)センター化学の勉強法や対策と異なる本物を皆さんは手に入れています。
また、実際に受験すらしていない、もしくは実際に自身は低得点にとどまっているのに当塾の勉強法を拝借していって「表面的に同じようなことを語る本質が伴っていない勉強法」に踊らされることもありません。(勝手に勉強法を拝借していっていいと思っている人間に当塾は断固抗議します。受験生にとって害悪でしかないからです。)
これだけで皆さんは、他の受験生に大きなアドバンテージを得ています。ただし、勉強法や対策というのは知っただけでは宝の持ち腐れです。
しっかり実践していけるか否かでセンター化学で高得点を獲得できる受験生とそうでない受験生にさらに分かれます。
以下では、優れたセンター化学の勉強法と対策を他の受験生よりもさらに生かす方法を列挙します。
センター化学と2次試験・私大対策を効率的に行いたい受験生へ
2次・私大対策も含めて化学の勉強法と対策を学びたい方は当塾の誇る多数の東大理三合格講師(東大医学部医学科)や東大理二「首席」合格講師(東大医学部医学科)のアドバイスをふんだんに盛り込んだ化学の勉強法と対策」 のコンテンツをご覧ください。
センター化学基礎で高得点を獲得した文系受験生へ
センター化学基礎の勉強法と対策を学びたい方は当塾が誇る多数の東大文一・文二合格講師のアドバイスをふんだんに盛り込んだ 「センター化学基礎の勉強法と対策」 のコンテンツをご覧ください。
高得点が取れないのはのセンター化学の対策が不十分だったからではない
このコンテンツで当塾の東大合格講師のすべてがセンター化学の勉強に特化したセンター化学対策を秋以前の段階で勧めていないことはお気づきだと思います。
これにはセンター化学と受験化学の科目特性を完全に解明した確固たる根拠があるからです。結果に実証されていない巷のセンター試験の勉強法に惑わされることがないように以下のコンテンツも併せてご覧ください。
センター化学の勉強や対策で心がおれそうなときに読むコンテンツ
各教科の二次・私大対策もやらなければならない、センター化学対策も他の教科もやらなくてはならない、「ああもうだめだ、間に合わない」と投げ出したくなることは誰にでもあります。
でもここで逃げ出してしまってはセンター化学で高得点が取れないどころか、第一志望合格はありません。合格者も例外なく逃げ出したくなる時もあったのです。でも逃げなかった、だから合格できた。
以下のコンテンツはセンター試験が終わるまで心がおれそうなときや対策がわからなくなった時には常に戻って読んでください。
受験全教科とのバランスを考慮した受験戦略や勉強法を知りたいという受験生へ
センター化学の勉強法や対策はもとより受験戦略、受験勉強計画、各科目勉強法をさらに体系的に詳細に学びたい方は「受験の叡智」【受験戦略・勉強法の体系書】をご覧ください。あなたを第一志望校合格へ導く一冊です。
圧倒的結果に実証されたセンター化学の勉強法と対策をお友達にも
今後もセンター化学の勉強法と対策のコンテンツを追加して行きます。お友達やお知り合いと適切な情報を共有し切磋琢磨しあうことは、あなたの合格可能性を高めることに非常に役立ちます。以下のシェアボタンを押せば簡単にシェアできます。