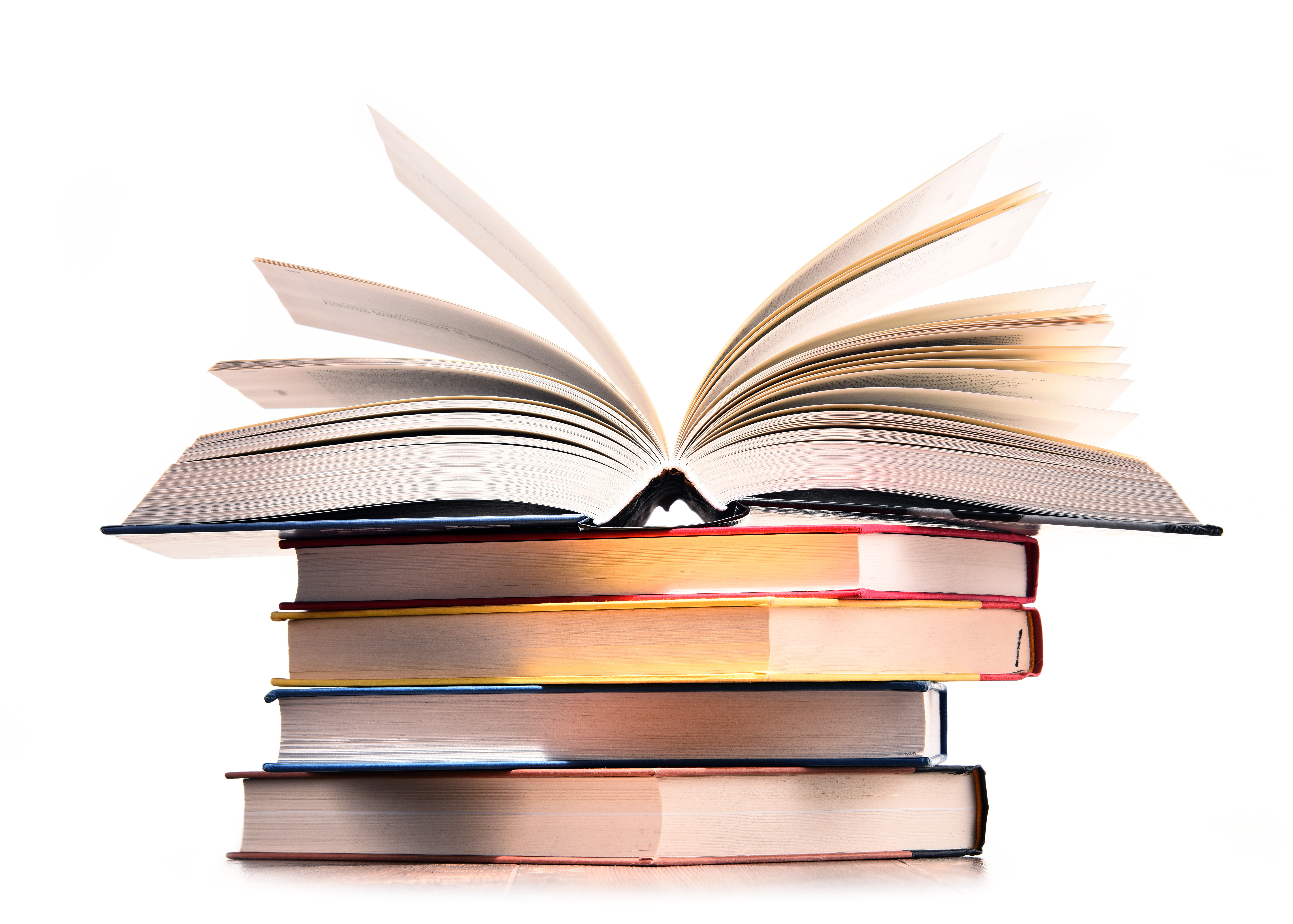公式サイトトップ>> 無料コンテンツTOP>> 大学受験の勉強法と対策【各教科】>> 数学の勉強法|医学部・難関大学に合格するためのコンテンツ一覧>> 数学の基礎固めの勉強法|実力を伸ばす5つのポイント
数学の基礎固めの勉強法
受験数学を極めた
東大理三合格講師30名超を有する
叡学舎(株)合格の天使の数学勉強法
数学の実力をあげるために必須となる基礎固め
数学は苦手とする人が最も多い科目と言えます。しかしこの原因は決してセンスなどではありません。数学の実力がつかない最たる原因、それは、
●しっかりと段階を踏んでいない
●各段階での的確な取り組みがなされていない
この2つが相まっていることによるものです。
数学勉強法|東大「医学部」「理三」合格者20名超の受験対策 ▶ のページに記載していますが、数学の実力をあげるための勉強として大きな柱が3つあります。
●基礎の習得
●思考力の養成
●計算力・計算スピードの養成
以上の3つです。
数学の勉強として大事になるのは、この大きな3つの柱で勉強法を捉えることです。 そして各段階を決してスキップしないことです。さらに各段階に応じた的確な取り組み方で問題演習を重ねることです。このコンテンツでは多くの受験生が間違った勉強法をとってしまう数学の基礎固めの段階の勉強法に特化して解説します。
基礎習得段階における数学の勉強法のポイント
基礎の習得段階における数学勉強法のポイントは、教科書(もしくはそれに代わる代用書)と その傍用問題集(もしくはそれに匹敵するレベルの基礎問題集)をどのように学び、使っていくかです。
この基礎の習得過程だけを見ても世の中には間違った数学勉強法が氾濫しているので注意してください。
数学の教科書の使い方
数学の教科書の使い方について地方私立高校⇒東大理三現役合格講師 深川(センター試験869/900) の書下ろし記事を掲載します。
数学は基礎の段階の習得が一番大切です。 これはもちろん別の教科についても同じことがいえるのですが、数学については特にこの段階が大切です。
数学の基礎の習得では教科書もしくはそれに準じた参考書と、基礎的な問題集を用います。 教科書や参考書は自分の持っているものを用いれば問題ないかと思います。
数学の教科書は実にわかりやすく書かれており、教科書の例題を読み解いていくだけでも相当な力になります。 また、数学ではインプットよりもアウトプットの方がはるかに重要です。
これはつまり、問題の解答を眺めているだけでは一向に問題を解けるようにはならないという意味です。 教科書の例題を読み解いていくことが初めは必要なのですが、読み解いた後にそのまま次に進むのではなく、 答えを隠して自らの手で解答を導き出すことが必須です。
ですから、説明事項を読み理解し、例題を読み解く。その後に例題の答えを隠して自らの手で解き直す。 これが教科書の使い方です。
教科書理解の方法
数学の教科書理解の方法について地方私立高校⇒東大理三現役合格講師 江尻(センター試験868/900) が書き下ろした記事をご覧ください。
高校数学の基礎レベルを身につけるのにするべきことは、教科書(またはそれ相当の内容をもったもの) の理解と基礎問題集の習得です。
まず、教科書の理解についてです。 効率的に内容を理解するためには、教科書の記述をしっかり最初から追うのが1番です。 「何が定義されたのか」「道具をどのように使うのか」「どのような定理なのか」 「定理を使ってどのような問題が解けるのか」などを1つずつ理解していってください。
その際、定理の証明は複雑そうだったら飛ばしてもいいと思います。 (理解レベルが上がってから立ち戻ればいいので。) ところどころにある例題もしっかり理解しながら進んでいきましょう。 そして、練習問題も自分で手を動かして解いてみましょう。 このように進めて1つの章が終わったら、 章末問題はやらなくていいのでもう1回どういう話があったのかざっと見直してみてください。
その後に基礎問題集の対応する範囲を進めていきます。
ただし、1つの章を学習しただけでも疑問はいくつか湧いてくると思うので、
次の問題集に進む前に先生なり数学が得意な人なりに質問して解消するようにしてください。
最初に間違った方向で理解したものを矯正するには、最初に学んだ時以上の労力が必要になりますからね。
基礎固め段階のインプットの注意点
基礎固め段階のインプット時の注意点について地方公立高校⇒東大理三現役合格講師 安藤(センター試験877/900)の書下ろし記事をご覧ください。
数学はインプットし終えた段階とアウトプットできるようになる段階のギャップが大きい科目です。 その差を問題演習によって埋めていくことになります。 数学の点数はこの演習の量で決まると思います。現浪で差が大きくつきやすいのもそのためでしょう。 そのため、(基礎段階では)なるべく早くインプットを終わらせ、 (標準問題演習レベルでの)アウトプットの練習量をなるべく多く確保することが重要だと思います。
インプットのときの注意点としては以下の2点が重要です。
よくわからない点に拘泥しない
この時点で考え込むのは非常に効率が悪いです。 よく分かっている人に聞くか放置して次に進みましょう。
基礎のインプット段階でもアウトプットを適宜挟む
この段階でも問題演習を適宜挟むことです。 ここの問題は簡単なものでOKです。
基礎固め段階での間違った数学勉強法
世の中の数学勉強法というのはレベルや次元を問わず、理解することや回数をこなしてマスターすることを重視しますがそもそもその前提が間違っています。
数学の概念や公式は初習の段階では完全理解は不要
数学の概念や公式は初習の段階では完全理解は不要ということについて地方公立高校⇒東大理三現役合格講師 安藤(センター試験877/900)の書下ろし記事をご覧ください。
数学の教科書レベルの学習では、なるべく時間をかけず問題を多く解き、 理解度はあまり心配しないのがいいと思います。
まず、数学で習う概念や公式を理解するには問題を多く解いてその概念や公式を使う機会を多く持つ必要があります。 そのため、問題をこなす以前の段階で時間をかけて理解しようとするのは (入試で点を取るという観点では)非効率的だと思います。 ですので、初習の際は完全理解は目指さず、各公式の使い方を覚えるような形で進めていくのがいいでしょう。 そして演習を通して公式に慣れましょう。 答えはすぐに見ていいと思います。
ある程度問題が解けるようになり概念や公式に親しんだら次の問題集に移っていいでしょう。 このレベルの問題集は早く卒業して次の標準レベルの問題集(青チャート、Focus Goldなど) で時間をかけるべきだと思います。(この理由は先ほどの「基礎習得段階のインプット時の注意点」に書いてある通りです)
ここまでのお話の注意点!
以上の江尻、安藤の話の中で、
江尻が「定理の証明は複雑そうだったら飛ばしてもいいと思います。
(理解レベルが上がってから立ち戻ればいいので。)」、
安藤が「数学の教科書レベルの学習では、なるべく時間をかけず問題を多く解き、理解度はあまり心配しないのがいいと思います。」
と言っていますが、これには以下でご説明していく内容が前提となっていることを誤解しないでください。
簡潔に結論だけお伝えしておくと、次のレベル・段階の問題演習の過程で適宜、理解が曖昧・不十分な部分に立ち返り 確認を行っていく、理解をしていくということが前提となっています。
これは裏を返すとどいうことかというと、教科書(もしくはそれに代わる参考書)について 、東大理三に合格した彼らでも最初からすべてを理解していくことは不可能・非効率ということを意味しています。
要するに基礎をしっかり理解するというのはそれだけ難しいということであるとともに、 全体を学ぶ中で立ち返る方が本質的な理解という点でも、効率という点でも優れている部分があるということです。
数学の初習問題集への取り組み方と公式の理解記憶の方法
今までのお話を前提に数学の初習問題集への取り組み方と公式の理解記憶の方法について以下の動画から大事なことを学んでください。
【動画で解説】初習の問題集の独学の方法
当然のことですが、初学の段階で絶対に理解していかなくてはならないという部分はあります。 自分で勉強を進めていく際に、何をどこまで理解すべきで、逆にしなくていいのかの基準について 以下の動画をご覧ください。
この動画は、数学のみならず全教科を対象にお話をしていますが数学も当然前提にしています。 参考にしてください。
地方公立高校⇒東大理三現役合格講師 正門(センター試験864/900)の解説動画です。
【動画で解説】数学の公式の理解記憶の方法
数学の基本的な公式は覚えていかなければ問題を解けません。しかし、ごくごく基本的な公式以外、単純暗記をしていたのでは数が多く覚えにくい、複雑で数が多くなってくると混乱する、 公式の一部を忘れてしまう、等の弊害が生じます。
この弊害を除くためにはごくごく基本的な単純暗記すべき公式以外は理解暗記をしていくのがおすすめです。実際にはこれが本質的な理解にもつながっていきます。以下ではその方法について解説します。
開成高校⇒東大理三「次席」現役合格講師 小団扇(センター試験867/900)の解説動画です。
基礎固めにおすすめの数学問題集・参考書
教科書及び傍用問題集
※全くの独学の場合は教科書及び傍用問題集の代わりに以下のものから入っても良い。 以下では教科書代わりの参考書を掲載する。
語りかける高校数学(ベレ出版)
「数Ⅰ編」「数Ⅱ編」と別れている。 授業のように先生が語り掛けてくる構成。 0から始めるのであればお勧めできる。
問題数が少なめではあるが、簡単な問題を細かい段階に分けて説明してくれているので 論理の理解とともに計算力アップも図れる。
スバラシク面白いと評判の初めから始める数学(マセマ)
「数学Ⅰ」「数学A」「数学Ⅱ」「数学B」「数学ⅢPART1」「数学ⅢPART2」と別れている。 上記「語りかける高校数学」と同じく授業のような構成。0から始める人向け。これも問題数は少なめ。 書店などで両者を比べ気にいった方を選べばよい。
沖田の数学をはじめからていねいにシリーズ(東進ブックス)
「ⅠA 数と式・集合と論証・2次関数編」「ⅠA 図形と軽量・図形の性質編」 「ⅠA 場合の数と確立データの分析・整数の性質編」に分かれている。
講義口調なので、実際に授業を受けているような感覚がある。 初修の人、すっかり忘れてしまっている人にオススメ。
数学の基礎レベル段階の勉強法のまとめ
基礎固めの段階の数学勉強法のポイントをまとめます。
最初に教科書やそのレベルの参考書に当たる段階では完全理解は不要
最初に教科書やそのレベルの参考書に当たる段階では完全理解は不要でとりあえずまず全体を学ぶことを優先しましょう。
このレベルの問題集(白チャートなど)は何回も繰り返す意味はない!
このレベルの問題集(白チャートなど)は定理・定義の使い⽅・基本操作を学ぶための本なので、解法や定石を学ぶ段階の問題集と異なり、それを目的として何回も解き直す必要はありません。
要するに、このレベルの問題集や問題演習の役割は、あくまで公式や概念の使い方を学ぶための物であって、そこから普遍的な解法の定石やエッセンスを学ぶものではない、そのような性質の問題集ではない、ということです。
基礎が大事であることと、この段階で基礎を完全理解することは別の話です。 問題集は解法が瞬時に浮かぶまで何度も繰り返し解くというのはこのレベルの問題集には的外れな話なのです。 あくまでこのレベルの問題集は、数学の基本操作を身に着けるためのものであって理解とかとは別次元の話です。 このことはしっかり理解しておいてください。
この部分を一緒くたにしてしまっている数学の勉強法というものが巷にはありますが、 それでは数学の実力は効率的についていかないどころか実力はついていきません。 無駄な単純暗記をさせられているにすぎないのです。 数学はお経ではないのでいくら唱えようが実力はつきません。 みなさんはこの部分間違えないようにしてください。
以上、このコンテンツでは数学の基礎固めの勉強法の特化して解説してきましたが、数学のすべての段階の勉強法をより詳細に学びたい方は 数学勉強法|70項目と13動画で学ぶ数学対策 ▶をご覧ください。
東大医学部・理三合格者が実践した基礎固めの数学勉強法をお友達やお知り合いにも教えてあげてください。以下のシェアボタンを押せば簡単にシェアできます。